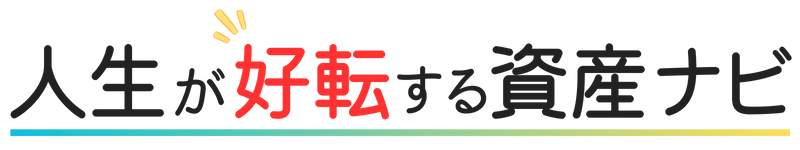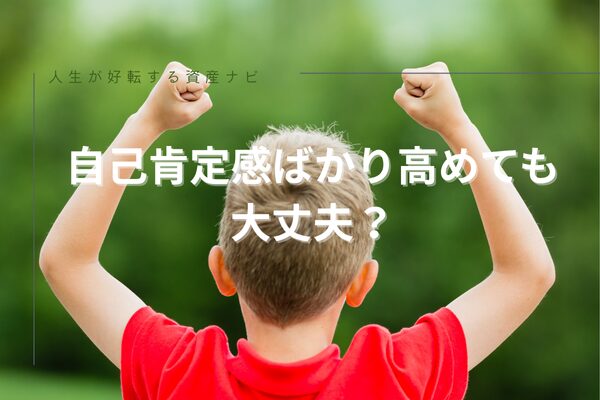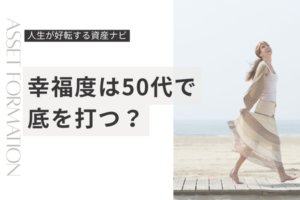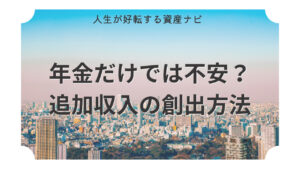はじめに:子育て=「自己肯定感を育てる」時代?
ここ数年、「子どもの自己肯定感を高めよう」というメッセージをよく耳にするようになりましたよね。
SNSでも本でも、育児講座でも「褒めて伸ばそう」「話を聞き、共感しよう」といった声がたくさん。
でも、ふと疑問に思ったことはありませんか?
本当に、それだけで子どもは社会を生き抜けるの?
今回は、「自己肯定感を高める育児」への過度な期待と、その影に潜むリスク、そして私たちができるバランスの良い子育てのヒントについて、考えてみたいと思います。
自己肯定感が高すぎることの“落とし穴”
「自己肯定感が高い=幸せ」というわけではない――
実は、こんな研究結果があります。
📌米国心理学者のJean Twenge氏らの研究(2012)では、90年代以降に育った若者の自己肯定感スコアは上昇傾向だったものの、忍耐力や共感力、ストレス耐性はむしろ低下していたとの報告があります。
つまり、ただ「自分を好きでいること」だけに焦点を当ててしまうと、
他者とぶつかったとき、思い通りにいかないときに耐えられない…
そんな“打たれ弱い”傾向につながることも。
社会に出たときのギャップ
社会に出ると、評価は「がんばり」や「実力」によって下されます。
いくら「自分はすごい」と思っていても、相手がそう思わなければ通用しないのが現実です。
💬 実際、大学新卒者の就職後3年以内の離職率は近年上昇傾向にあり(厚労省, 2023)、その理由の一つとして「理想と現実のギャップに耐えられない」という声が増えています。
「自己肯定感」だけで乗り越えられない場面が、社会にはたくさんあるのです。
解決策:自分を肯定する力+◯◯力
では、どうすればいいのでしょうか?
私たちが目指すべきは、自己肯定感にいくつかの要素を加え柔軟で複合的な素養。
ただ「自分が好き」で終わらせるのではなく、「自分にはできることもあれば、できないこともある」「時に失敗しても、自分を立て直せる」と思えるように導いてあげること。
🔑 子育てに加えたい3つの視点:
- 自己効力感(self-efficacy)を育てる
→「やればできる」と思える体験を小さな成功で積ませる。 - 他者視点を持たせる
→共感や協力の力を育てることで、社会の中で折り合いをつけられるように。 - ストレス対処力(レジリエンス)を養う
→失敗や否定的な経験を“リセット”できる心の回復力。
おわりに:肯定感の“バランス”を大切に
子どもが自分を信じる力を持つことは、もちろん大切です。
でも、それが「過信」や「現実との乖離」につながってしまっては本末転倒。
私たち大人ができるのは、
「大丈夫だよ」と安心を与えるだけでなく、
「でも、こういう時はどうする?」と問いかけること。
その積み重ねが、自己肯定感を“社会で通用する力”に変えてくれるはずです。
参考文献
- Twenge, J.M. & Campbell, W.K. (2012). “The Narcissism Epidemic”
- 厚生労働省『新卒就職者の離職状況』(2023年)
- Bandura, A. (1997). “Self-efficacy: The Exercise of Control”